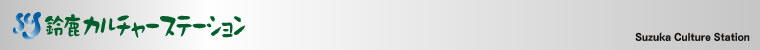
�O�̋L�����@�b���̋L�����@�b�@�m�d�v�r�ꗗ��
�A �Љ�̓{��E�����݂ƌ��������ɂ́d�@�@
�@�@�A
�킽�����f�惌�r���[�w�����݁x�i�J�\���B�b�c�ēE1995�N�E�t�����X�j
���킽������

��҂̖\���V�[�����I�[�v�j���O�ŗ����B
�����1994�N�P���Ƀ��A���ŋN�������\���̃V�[�����B�e�������̂��Ƃ����B
�o�b�N�Ƀ{�u�}�[���[�̃��Q�G�~���[�W�b�N�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�n���X�ɏZ�ވږ��Q���̎��3�l����l���B
�f���̓��m�N��

���_���n�̃��B���X�B
�A�����J�f��w�^�N�V�[�h���C�o�[�x�Ɠ����V�[���B�u�K������ˁ[�v

�A�t���J�n�̃��x�[���B�{�N�T�[�ŕ��Â��Ȑ��i�B

�A���u�n�̃T�C�[�h�B
�ږ��̕n���E���ʖ��
�f��w�����݁x�̉f���́A�₩�Ŕ������t�����X�̃C���[�W�Ƃ͑ɂ̖\�́E�n���E�X�����X�Ƃ������l�킪���݂���A�����J���f���o���Ă���悤�������B1995�N�̌��J�ŁA����̃t�����X��\����̑��ʂ��Ƃ����B
����ł́A�哈����́u���ꂪ�����ł��v�Ɖ��x�����ɂ����B
���̉����v��Ɓ\
�t�����X�ł́A1930�N�����ʂ̈ږ�������͂��߂��B��ꎟ���E����560���l���̎��҂��o���A�J���s����₤����270���l�����ꂽ�Ƃ����i�����̐l��4100���l��6.5���ɂ�����j�B
�������A������̖S���҂�ϋɓI�Ɏ��ꂽ�B�����܂ł̈ږ��̓t�����X�l�Ƃ��Ă̂��n�t�������炦�����A1970�N�ォ��́A�ږ��ɑ��ă����N����������B�d�����A������ŏd�J���ȐE�Ƃ��^����ꂽ�B�����ďZ���́A�p���x�O�Ɉږ��̏Z�ޒ�ƒ��̒c�n�������B
���݂̎��ƎҐ����A�ږ��̕��������A�t�����X�l�̎��Ǝ҂̂Q�{�Ƃ����s���ȏ�����B
�����Ɍ���t�����X�Љ������A�ږ��̕n���E���ʂƂ�������肪����B
�Ƃ���1980�N��ȍ~����ږ��Q���̎�҂����̖\�����p�����Ă���B
�������������f�扻������i�ł�����B
���̊ē}�`���[�E�J�\���B�b�c�̏o�����Δ[������B
�ē��g���ږ��Q���Ȃ̂��B�ē̕��e�̓��_���n�n���K���[�l�ŁA1956�N�̃n���K���[�������Ƀt�����X�֖S�����Ă����B����͌��哝�̂̃j�R���E�T���R�W�����_���n�M���V�A�l�����Ɏ��n���K���[�ږ��Q���ŁA�������̋��ʓ_������B
�u�}�`���[�J�\�r�b�c���T���R�W���A�����J�D�݂ł��v�Ƒ哈����B
�f��w�����݁x�ɂ́A�������̃A�����J�f��̃����V�[�����A�����W����Ă���B���y���{�u�E�}�[���[�̃��Q�G�~���[�W�b�N���I�[�v�j���O�ɗ���A�A�C�U�b�N�E�w�C�Y�̃T�U���\�E�����g����B
���R�̍��A�����J�ւ̓��ꂾ�낤���H
��҂����̋��т�����
�f��́A�\���̂����������̊ۂP�����O�l�̎�҂̍s����ǂ��Ă����B�p���x�O�̕n���X�ŕ�炷�ږ��Q���̎�҂����ŁA���_���n�̃��B���X�A���l�̃��x�[���A�A���u�n�̃T�C�[�h�̂R�l����l���B
�u���͍��̕�炵�ɃE���U���Ȃ�B�N�\�݂��߂ȕ�炵��ς������˂����H�v
���B���X�����ԂɂԂ���Z���t���B
������̋����ɕs���������A���Ԃ�x�@�ɑ��ē{����炷�B
�x�����Ȃ��������e�����B���X���E�������Ƃ����������ɕ���͓W�J����B
�����́A���܂�ɂ��Ռ��I�ŁA�ނ�̕����鑞���݂�ꂵ�݂����̂܂܊ϋq�ɓ��������Ă���悤���B
�I�[�v�j���O�A��l�̉�b�A�G���f�B���O�ƂR����������t���g����B
�u�r����50�K�����э~�肽�j�̘b�v�̈��p���B
�u���͗����ł͂Ȃ��v�u���n���v�ƌ����B
�ǂ����n������悢���𓊂������邪�A50�K�����э~�肽�璅�n�ȂǏo����͂����Ȃ��B
�G���f�B���O�ł́A�u����͗������Љ�̘b�v�ƌ����B
�f��̒��n�́A�e���̍����ƂȂ����B�e���͔ނ�̔ߒɂȋ��тɂ��������Ă���B
�c�����������Ɏc��A����Ȃ��C���������܂ł��Y���B
�N�ɂ����������ꂸ�ɉF�����i���Ƃ������ԚL�̂悤�B
�u��̉�����Ȃǒ��Ă��܂���B�ނ�̌���𗦒��ɕ`���Ă���f��ł��v�i�哈�j
���B���X�����e�ŃX�L���w�b�h�̒j�����Ƃ��Ƃ���V�[��������B�{������߂Č��e��˂����邪�A�����܂ł��B
�u���B���X���g�A�l���E����悤�l�ł͂Ȃ��B��������D�����v�i�哈�j
�������A�f��̌����ł́A�������B���X���Ȃ��߂Ă������l�̃��x�[�����A���̈��������������ƂɂȂ�B
�u���������������Ă���t�����X�Љ�B����������Ȃ�ł��v�i�哈�j
�l�̒��ɟT������{�����݂́A�Љ�Ƃ����傫�ȃV�X�e���̉߂����琶�܂ꂽ�^�̂悤�Ȃ��̂��B�₪�Ă��ꂪ�~�ς��ꔚ������B
�N������ȏɎ�����u�������͂Ȃ����낤���A�����đ��l���Ƃɂ͏o���Ȃ��B������������������ɂȂ����Ƃ�����d�d�B
��҂����̐S�Ɏ����X���悤�Ƃ���Ȃ�A�����������Ă��邾�낤���B
���Ȃ��Ƃ��f��Ƃ����}�̂�ʂ��ē`��郁�b�Z�[�W����́A�{�����݂Ƃ�����������͗N���Ă͂��Ȃ������i�L�Ҏ��g�ɂ́j�B���Ƃ����ē���⋤�����������킯�ł��Ȃ��B���܂ł������ł����ɑ̓��ɕۗL�����܂ܖ苿���Ă���B
�ē��g�A���̕s�𗝂Ȍ����ƌ����������߂ɁA�w�����݁x�삵���̂ł͂Ȃ����낤���B �{��̊���ڂԂ�����\�͂ɂȂ邪�A�f��ɂ���A�����l������A�v�����`��邩��B�i�L���F���킽�j
�O�̋L����
���̃y�[�W�̃g�b�v��