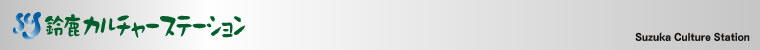
![]() ヌーベルバーグの先駆け
ヌーベルバーグの先駆け
――第4回フランス・デー開催! 《5月11日》
映画解説『死刑台のエレベーター』(1958年、監督ルイ・マル)

講師の大嶋優さん(関西学院大学フランス語講師・翻訳家)
![]() ルイ・マル監督25歳の作品!
ルイ・マル監督25歳の作品!
ヌーベルバーグの先駆けといわれる映画『死刑台のエレベーター』(1958年)が今回大嶋さんが取り上げた作品だ。監督はルイ・マル。大嶋さんがもっとも好きだという映画監督で、本講座でも『さよなら子供たち』(1987年)でお馴染みである。ルイ・マル監督の自伝的映画で、彼の少年時代の出来事を作品化したものだ。ナチス占領時代に寄宿舎で過ごすジュリアン少年にユダヤ人の友達ができる。しかし、友人は強制収容所に連行され二人の友情は引き裂かれてしまう。戦争の不条理と悲しさをストレートに突きつける作品だった。
ふと、ルイ・マル監督の幼い体験を思い出した。そして、『死刑台のエレベーター』に関する大嶋さんの解説がそこに重なってくると、ルイ・マル監督の意図が、次第に浮かび上がってくるようだった。
大嶋さんの話は、「ヌーベルバーグ」についてのザックリとした解説から。これまでも何度も取り上げているので、ここでも簡単に述べたい。ヌーベルバーグは映画製作の「新しい波」を意味している。その社会的時代背景は、1958年シャルル・ドゴール将軍が大統領となりフランス第五共和政の時代へと変わる。大統領が強大な権限を持ち、中央集権化し、社会的な締め付けが強まっていく時代だ。そうした政治に対するアンチテーゼとして起こったムーブメントがヌーベルバーグでもある。それ以前の映画製作の常識を破る製作手法で、若手の監督がお金をかけずに、ハンドカメラを回して作品を作っていく。新しい時代は、伝統や体制をブチ破れる若者によって生まれるのだと痛感する。ルイ・マル25歳のデビュー作が『死刑台のエレベーター』だ。
映画を鑑賞した吉田さんのレポートを紹介したい。(いわた)

フロランス役のジャンヌ・モロー
![]() 凝縮された心の世界 吉田順一
凝縮された心の世界 吉田順一
『死刑台のエレベーター』を観て
「ヌーベルバーグ」という言葉は、以前から聞いたことはあったし、またこの講座の中でも、何度か紹介もされてきていたので、全く初めてということではなかった。
現状の社会や、映画界にたいする"反(アンチテーゼ)"とは一体どういったものなのか?映画の中に込められた思いや、映画を製作してゆく過程での種々の試みとはどんなものがあったのだろうか?僕の中では判然とはしていないが、今の段階で感じ取れたところを書いてみようと思う。
凝縮された心の世界
「ジュテーム、、、」というフロランス(ジャンヌ・モロー)のアップから始まった映画は、ラストで、やはり「10年、20年無意味な暮らしが、、」という彼女のアップの独り言が出され、現像され浮かび上がった二人の写真で、"Fin"の文字が映し出される。
僕の勝手な解釈を言うならば、遊びのない直線的な映画、凝縮された心の世界を映し出した映画といえるかなと思った。ただ、思いわずらったり、いろいろな葛藤に心を悩ますというのではなくて、ここが僕にはとても直線的に思えるのだ。
エレベーターに閉じ込められてしまったジュリアンは、ひたすら脱出の方法を見出そうとするのだけれど、どこかに"醒めた"ものを感じさせる。タバコがなくなって、その空き箱にライターで火を点け真っ暗な闇の中へそれを落とす。燃えながら落下してゆくそれを見ているジュリアン、何も下にないことを確かめたかったのだろうけれど、なぜか僕にとっては象徴的な気持ちが起こる場面であった。
雷が鳴り雨が降る中をジュリアンを探してひたすら歩くフロランス。彼女の目、彼女の横顔が印象的だった。
痛烈な社会批判
フロランスと一緒になるために、夫であるカララ商会の社長をジュリアンは殺害し自殺に見せかけるのだが、それに至る前、彼と交わした言葉の中に、「戦争に感謝しな!」と、ジュリアンが社長に言う場面があった。戦争を生業にしている人また会社、そしてそれを容認している社会への痛烈な批判と僕には受け取れた。同じように戦争というものに対しての批判は、ジュリアンの車を奪って逃げた若者の口からも聞き取れた。それは、モーテルで一緒にドイツ人観光客とお酒を飲もうとなった時、飲まない理由を若者(ルイ)が言ったけれど、そこにも現れていたと思う。
単純(シンプル)な構成
どちらかといえば複雑さを排除したと言ったら良いのだろうか?
「若い娘となんで?!」と車の運転手をジュリアンと勘違いしたフロランス。そして、「殺せなかったんだわ。」と思い込む彼女だけれど、愛する人を探す気持ちに変わりがない。どこまでも探してゆく。
若い二人が死のうとして娘が睡眠薬を致死量をルイに渡すが、「この音楽が終わるころには死んでいるわ。」と聞いて、ルイは手の平に乗せられた薬をすっと口に持ってゆき飲み干す。「あれっ??」と観ている自分が思うくらい、あっけないものだった。
若者がそれさえなければと、モーテルでドイツ人観光客の女性が写した写真を取り戻そうと、バイクでモーテルへ向かう。そしてそれを車で追いかけるフロランス。しかしそこには刑事がすでに来ていた。ルイもつかまり、フロランスも「奥さん他にも写真があります。」と、刑事に腕を持たれて現像室へ。そこで見たもの、それは紛れもない、ジュリアンと彼女の写真だった。

取調室で尋問されるジュリアン(モーリス・ロネ)=中央=と警部(リノ・ヴァンチェラ)=左=
取り調べの場面にて
映画全体でも声を荒げるといったような場面はほとんどなかったが、唯一、刑事に執拗に尋問を受けるジュリアンが、何度か大きな声を出した場面が印象に残るくらいだった。僕は、この取り調べの場面が心に残る。人物を際立たせて、他一切は真っ黒の背景で、余分なものを削ぎ落としてしまったような印象を受けた。
最後に
25歳のルイマル監督、そして音楽は31歳マイルスデイビスのトランペット。僕としてはもう少しトランペットを聞きたい場面のところもあったけれど、素敵だなと思った。
ヌーベルバーグの先駆けとなった映画と、大嶋さんからは聴いた。改めて一本の映画の持つ意味を僕の中では考え始めている。
『死刑台のエレベーター』を私は講座後じっくりと鑑賞した。ルイ・マル監督の奥深くにある戦争への憎しみが『さよなら子供たち』とシンクロして感じられた。『死刑台〜』が娯楽映画、サスペンス映画を装いながらも社会への痛烈な批判を呈している点は見逃せないと感じる。私個人の映画レビューは後日アップしたい。(いわた)
>>> 映画レビュー「愛するが故の殺人は許される?」

