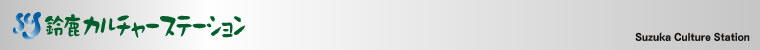
映画を通して
フランスの歴史を知る
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
次回の予定
映画『さよなら子供たち』
の各シーンより
休日を終えて駅で母と分かれる
ジュリアンは寄宿学校へ向かう。
転入生のボネはユダヤ教徒。
夜中に起きてお祈りを捧げる。
ベッドの隣で、ボネの行動を見て
いたジュリアンは、ボネが何者で
あるか、彼のロッカーを探る。
ボネの書物に書かれていた文字を
鏡に映すと、ジャン・キベルシュタ
インというボネの本名を見つける。
ボネがユダヤ人であることを知る。
休みの日。宝探しの遊びに出か
ける。二人の間に次第に友情が
芽生えていく。
ジュリアンはボネに豚肉のパイを
差し出すが、ボネは拒否する。
(ユダヤ教では豚肉は禁止されて
いる) 理由は言わず、喧嘩になる。
聖体拝領の儀式。カトリック教徒
になるための儀式。 この場にな
ぜボネが立っているのかは謎だ。
ジャン神父はボネがそこにいる
ことに驚く。
聖体を与えるジャン神父と 口に
するジュリアン。これでカトリック
教徒となる。
ナチス・ドイツ軍のゲシュタポが
学校に現れる。ユダヤ人狩りだ。
ゲシュタポに密告したのは、学校
の料理番を解雇されたジョセフ
(正面)によるもの。そのことに
唖然とするジュリアン(背中)
ジャン神父とユダヤ人の生徒3人
がナチス軍に連行されていく。
別れのシーン。見送る生徒たちに
「さよなら子供たち」と声をかける。
この言葉が映画のタイトル。
見送るジュリアン。目には涙。
「この日の朝を私は死ぬまで忘
れない」と監督はコメントする。
ユダヤ人とは、ユダヤ教とは、その歴史
映画『さよなら子供たち』(1987年・フランス)
映画を通してフランスの歴史を知る 第4回 《2月26日》
講師の大嶋優さん(関西学院大学フランス語講師)
ナチスによるユダヤ人大量虐殺、ホロコースト・・そんな言葉を耳にすると、悲惨な戦争をイメージするだろうか。知識としてではなく、その体験を今に伝えるものとして、今回の映画は、あまりにも直接的に感情を揺さぶるものだった。
悲しみと、どんよりとした重さで一杯になった。
歴史とは、紐解けば紐解くほど、人間の悲しみ醜さを浮き彫りにするものなのか。
ユダヤ人とは、ユダヤ教とは
まずは講座の様子から。
映画の前に大嶋さんによる解説で始まった。
「今回のテーマは、ユダヤ人、ユダヤ教、反ユダヤ主義です」。
「映画の背景を知らないと、映画の持つ意味や各シーンの意図が理解出来ないから」と、短い時間でポイントを絞って伝える。
英国やフランスでは、「ユダヤ人(Jew)」を辞書で引くと「貪欲な人、高利貸し」の意味がある。こんなところにユダヤ人に対する蔑視がある。昔、キリスト教では、金融に携わるものは卑しいとして、金融の仕事を禁止していた。代わってユダヤ人がしたので、金貸しで大儲けしたユダヤ人を揶揄し、それが言葉となって残っているという。
ユダヤ人とは、歴史上たえず虐げられ、安住の地のないまま世界に離散し、今も中東ではパレスチナ問題を抱えている。
そのユダヤ人とは何かの定義を旧約聖書を取り出して、大嶋さんが紐解いてくれた(上の写真)。
歴史上対立しているユダヤ教、イスラム教、キリスト教は、実は兄弟のような宗教で、みな旧約聖書を教典にしていること。旧約聖書にはアダムとエバなどの神話が綴られ、私たちが聞くとちょっとユーモアにも受け取れる内容もある。その系譜を辿るとユダヤ人としての定義があること。
また、ユダヤ人は、ローマ帝国に滅ぼされて以来、自国の領土を持たない流浪の民となり世界に離散した。唯一、ユダヤ教をアイデンティティとしてまとまってきた民族で、選民思想・メシア思想が根底にある。
ローマ帝国がキリスト教を国教に定めてから反ユダヤとなり、十字軍の遠征では、ユダヤ教を迫害し、19世紀には反ユダヤ主義思想が広がり、人種的にユダヤ人を差別するようになった。そして、ナチス・ドイツ軍によるユダヤ人大虐殺へと歴史は向かう。
ボネ(ユダヤ人)とジュリアン(カトリック教徒)の友情
1944年、ナチス占領時代のフランス。パリから離れカトリックの寄宿学校に疎開している11歳のジュリアンの学校生活を描いたものだ。
学校に ボネという転入生がやってくる。ボネはユダヤ人だ。ある時ジュリアンはそれを知る。時に馬鹿にし、喧嘩になるが、やがて二人の間に友情が芽生えていく。
そして1月のある朝、突然ゲシュタポが学校に現れ、ユダヤ人生徒を見つけにくる。
寄宿学校の校長はカトリック教徒のジャン神父で、神父の人道的な配慮でユダヤ人生徒を学校に匿っていたのだった。
しかし、その日、匿った罪で逮捕され、ジャン神父とユダヤ人生徒は連行されてしまった。
その別れの時にジャン神父は「さよなら子供たち」と告げる。
ボネはアウシュビッツで、ジャン神父はマウトハウゼンで死んでしまった、と語られる。
別れを見送るジュリアンの目から零れる涙。
そこで映画は終わる。
「突然、私たちの小さな世界が崩れた」
「『さよなら子供たち』は、私の少年時代の中でも最も劇的な時代の思い出から生まれた映画です。1944年、私は11歳でした。私はフォンテーヌブロー近くのカトリック系の中学校の寄宿生でした。年の初めに、新入生がやって来て、非常に興味を引かれました。彼は他の生徒と違っていて秘密めいていました。彼と知り合いになり、好きになり、そしてある朝、突然、私たちの小さな世界が崩れたのです。」(ルイ・マル)
相反する場面から聞こえる心の叫び
大嶋さんは、「単に戦争の悲惨さを訴えた映画ではない、それ以上に訴えてくる何かがある」と言う。それが何であるのか――
淡々と描かれた場面には、それぞれに込められた思いや背景が映し出されている。その背景を知れば知るほど、マル監督の言葉にならない叫びが聞こえてくるようにも思う。
例えば、ユダヤ人を匿っていたジャン神父は、敬虔カトリック信者である。聖体拝領という儀式の中で、ユダヤ信者のボネに対しては聖体を与えない厳格さを見せる。
また、寄宿学校の生徒たちはみな裕福な家庭の子どもたちだが、その父母たちの前で説教する。「金持ちが天国の門を通るのは、駱駝が針の穴を通り抜けるより難しい…」、一人の父親はその言葉に怒りを覚え退席する。
そんな、混じりあわない、相反する場面が、所々に登場し、葛藤を覚えながら最終場面へ向かう。
大嶋さんの解説がなければ分からないシーンばかりだ。
子どもの心の中にあるもの…
11歳という少年の目線で描かれた映画。矛盾と不条理に満ちた出来事。
ただ、もしこの映画から真実を汲み取るとしたら、記者が思うのは、ジュリアンとボネの間に芽生えた友情である。ボネが去っていく時、ジュリアンの見つめる目は、「なぜ、どうして、何で、行かなければならないの?」と訴えていた。
ユダヤ人だから?宗教上の理由?人種・歴史、何がそうさせるの? それらの言葉はジュリアンを納得させる理由にはならないだろう。
無邪気で腕白な子どもの心には、如何なる歴史的理由など入る余地はない(のではないか)。
記者自身は、そちらの真実を選びたい。もし歴史が未来に希望を示すのだとすれば…
(私の宗教・信仰観からは到底理解できないものだと、言い訳はしておく) (記事:いわた)
次回の予告!
4月16日(土)pm7:00〜9:30
映画は『パリ空港の人々』を取り上げます。 講座のテーマは「トランジット」です。
いよいよ時代は現在です。 今回は『パリ空港の人々』を取り上げます。
現在は「ボーダーレスの時代」といわれますが、人の移動に関しては、まだまだボーダー(国境)が横たわっています。
そしてボーダーのどちら側にも属さないトランジットと呼ばれる空隙も存在します。
『パリ空港の人々』はそのトランジットに住む人々とトランジットに迷い込んだ旅行者との人情味あふれる大人のメルヘンです。
監督フィリップ・リオレは、実際トランジットで長年暮らしていた人物をモデルにこの映画を製作しました。 このページのトップへ