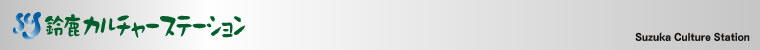
![]() 第1回フランス・デー開催! 《2月9日》
第1回フランス・デー開催! 《2月9日》
映画解説『モンパルナスの灯』(1958年、監督ジャック・ベッケル)
アズナブールの詩の朗読・旅行のためのフランス語会話・モディリアーニ作品解説

講師の大嶋優さん(関西学院大学フランス語講師・翻訳家)
![]() 今、鈴鹿からフランス文化を発信!
今、鈴鹿からフランス文化を発信!
いま、Eテレ番組「100分de名著」で、フランス文学、デュマの『モンテ・クリスト伯』が読み解かれている。読み出したら止まらないという現代のエンターテーメントの元祖なのだそうだ。
『モンテ・クリスト伯』といえば、以前に本講座でも紹介した復讐劇の傑作だ。そのストーリー展開にはグングンと引き込まれてしまう面白さがある。こうした現代にも読み継がれている19世紀のフランス文学にドラマ展開の原点があるというのだから、私たちの身の周りの文化の源流を辿れば、かなりフランス文化に行き着くようだ。
そんな時流の風も感じつつ、これまでも大嶋さんがテーマにしてきたフランス映画講座も、さらに進展し、様々な角度からフランス文化に触れる機会にしようと今回から「フランス・デー」と名称新たに第1回目が2月9日に開催された。
大嶋さんによる、映画『モンパルナスの灯』の解説。吉田さんのシャンソンに親しもう・アズナブールの詩の朗読。旅行のためのフランス語会話、モディリアーニの作品解説と、最後まで目が離せない企画となった。
アズナブールの詩を朗読する吉田さん。
旅行のためのフランス語会話の時間。
隣同士で会話してみたり、小一時間ほどフランス語を楽しんだ。
大嶋さんもノリノリで会場も大いに湧いた。

カフェ・サンスーシでは、フランス・デー応援メニューとして、フランスのトースト「クロックムッシュ」がこの日だけ登場! お召し上がり頂けなかった方は是非来月ご注文下さい!
![]() ジャック・ベッケル監督の意図は?
ジャック・ベッケル監督の意図は?
さて、今回大嶋さんが取り上げた作品は、ジャック・ベッケル監督の『モンパルナスの灯』、1958年のモノクロ映画だ。画家モディリアーニの生涯を扱ったもので、画家という職業が如何に貧窮と孤独にあったか、その悲哀を物語っている。この映画を見た後でモディリアーニの作品に目をやると、彼の人生とが重なっていっそう哀愁を感じてしまうことだろう。
大嶋さんは、まず監督のジャック・ベッケルについて解説した。
元々この映画は、マックス・オフュルス監督が手がけていたものだった。ところが心臓病で入院し断念してしまい、友人のジャック・ベッケル監督に依頼し完成した作品だという。そのためベッケル監督にしてみれば自分が作りたい映画ではなかったそうだ。
オフュルス監督は耽美主義で宮廷映画などの優美で審美的な映画制作者だ。それに対し、ベッケル監督は現実主義で、『現金に手を出すな』というギャング映画や脱獄を扱った『穴』というアクション映画を撮っている。いわば二人の映画観は対極にあった。
そこで、ベッケル監督は、オフィリス監督の書いたシナリオを書き換えてしまう。モディリアーニの足跡を辿るのではなく、自分のモディリアーニ像を表現したいという条件で監督を引き継いたのだ。
そして 映画の中に架空の人物を登場させる。リノ・ヴァンチュラが演じるモレルという画商だ。
大嶋さんは、「モレルが主人公じゃないかと思われるところがある」と言う。
なるほど、作品を鑑賞してみると画商のモレルが重要な役となって、映画は一つの強いメッセージを伝えているようだった。
映画を鑑賞した 吉田さんのレポートを紹介する。(記事:いわた)

モディリアニ役のジェラール・フィリップ
![]() 映画「モンパルナスの灯」に感じる“こころの灯”
映画「モンパルナスの灯」に感じる“こころの灯”
「死は死である」という或る作家の言葉がふっと僕の脳裏に浮かんだ。
愛する人と巡り会いながらも、最後は病院のベッドの上で、身元もわからぬまま、臨終を告げられる場面に、人間の生のはかなさを感じた。
この映画を創った”ジャック・ベッケル監督”の、制作意図の一端を感じる思いがした。
映画を見ている間には、僕の中に大きな心の揺れを感じることはなかった。それが、映画のラスト近くになった時、”リノ・バンチュラ”役の画商が、ふらふら街中をよろめき歩き、やがて路上に仰向けに倒れる、モジリアニにまるでハゲタカかハイエナの如くに、ずっとくっつくようにして歩く様は、不気味な感じがした。
僕の心に変化が現れたのはこの後だった。病院を後にして、画商はモジリアニの家に行く。そうして絵を見て、「これはいい」とつぶやくように、ジャンヌに伝える。モジの死を知らぬジャンヌは「お金よりも、とても励みになりますわ」と、画商に伝える。画商は、次々にそこにあった絵を買い上げてゆく。このあたりからだった。僕の心の中に、ぐっとこみあげてくるものがあり、目頭が熱くなるのを感じた。
結局、生きている間には、彼の作品は極く少数の人にしか認めてもらえず、食うのにも困る暮らしでのまま、報われることなく36歳の生涯をおえることになった者への、同情の気持ちからであったろうか。
それにしても、最後の場面から、僕は強烈なインパクトを受けた。あの時の画商の眼、そこに、シリアスかつ現実的な視点から、この映画を創るに至った監督の、強い意志を感じる。

画商のモレル役を演じるリノ・バンチュラ
二つの疑問
一つ目
それは、『モンパルナスの灯』という日本語のタイトルについてである。売れない画家モジリアニの生涯を描いた映画ではあるが、このタイトルは一体何を表そうとしているのだろうか?
白黒の映画であるから、それでなくとも、映画全体は暗い色調が漂う。大嶋さんが解説でも話してくれていたが、まるで幽霊がボーっと出てきそうな夜の風景が、何箇所かあった。
モジリアニは、成功を見ずに若くして死んでしまうのだが、彼が生きた時代、彼が住んだ街は、彼が死んだ後も続き、情景は変わりながらも、街は生き続けてゆく。
ふと、僕の頭の中には『街の灯』というチャップリンの映画のタイトルが浮かんでくる。調べてみると、1931年作となっている。この映画よりも二〇数年も前の映画である。
ベッケル監督が表したかったのは何だったのだろう。そこを改めて思う。

モディリアニの恋人ジャンヌ役の アヌーク・エーメ
それからもう一つの疑問。
これは疑問というより、納得の仕方とでも言ったらよいか。主役の二人、モジリアニ役の(ジェラール・フィリップ)と、ジャンヌ役の(アヌーク・エーメ)についてである。
ここのところ、アヌーク・エーメという女優を見る機会が続いている。とても美人だ。そしてもうひとりの俳優、ジャック・フィリップ。アラン・ドロンの前の世代の二枚目俳優だ。
この配役について監督自身はどうだったのだろう。美男、美女であるが故に、映画としての深みが欠けてしまう、と言ったら言い過ぎになるだろうか?ストーリーとして。
「とてもいわくつきの映画で……」とは、大嶋さんが解説の初めに話していたことだけれど、やはりどこか、後に物足りなさを感じてしまうのは何故だろう。
モジリアニが守ろうとしたもの、それは何だったのだろう。灯しつづけていったものは何だったのだろう。
あの暗い街中を照らす「モンパルナスの灯」 それは、一つの象徴的な“こころの灯”とでも言おうか……
(吉田順一) このページのトップへ

