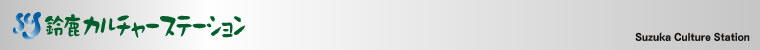


2月13日、第2回目のサイエンスカフェ
「環境と文明シリーズ」が開催されまし
た。講師は、荒田鉄二氏(左)。
コメンテー ターは内藤正明氏(右)。
第1回に引き続いての発表です。

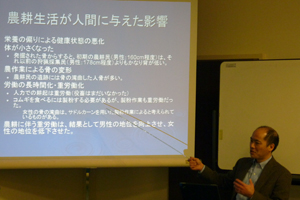

サイエンスカフェ 環境と文明シリーズ 第2回
『文明と自然環境』 《2月13日》
荒田鉄二(NPO法人KIESS研究員・鳥取環境大学准教授)

1. 農耕の始まり
草本花粉と木本花粉の比率の分析から、更新世末期(1万3000年前以降)の温暖湿潤化にともない、パレスチナ地域には森林が出現したと推定されている。その環境下で最初の定住集落が形成された。そして、定住集落という生活様式をもった人々の一部が東地中海(レヴァント)北部の草原地帯という異なる環境に進出し、食糧資源として、そこに生えていた草本類に着目した。やがてムギ、マメという最も生産性、貯蔵性の優れた一年生草本の選択的利用が始められた。そうしたなかから最初の栽培の試みが行われ、そこから農耕定住生活への移行が生じたとされる。
農耕定住生活への移行は、狩猟採集に較べて生活が安定し、人々を豊かにしたと考えるのが一般的である。しかしながら、初期農耕民の骨は、そうではなかったことを示している。最初の農耕民は、それ以前の狩猟採集民よりも小柄で、栄養問題や伝染病に苦しめられていた。また、生きていくために必要な労働時間も、狩猟採集生活の方が農耕生活よりも遥かに短かったと考えられている。それにもかかわらず、なぜヒトは農耕定住生活をするようになったのだろうか。寒冷化仮説では次のように考えられている。
1万3000〜1万1000年前は世界的に温暖な時期であり、これによって中東地域の人口が増加した。この時までには狩猟技術も高度に発達しており、人口が増えるなかで人々は草原に生息する大型哺乳動物を狩り尽くしていった。こうした時にヤンガー・ドリアスの寒の戻り(1万1000〜1万年前)が起こり、増大した人口と環境悪化による食糧不足のなかで、人々はしかたなく農耕を始めた。農耕生活は狩猟採集生活と比べて快適なわけではないが、同じ面積でより多くの人口を養えるため、農耕は人口増加を可能にする。そして、人口が増えれば更に食糧が必要になる。このため、一度農耕を始めると、それをやめることは、ほとんど不可能になる。これが人類がこれまで農耕を続けてきた理由と考えられる。
2 . 文明の始まり
農業の労働生産性(1人の耕作者が何人分の食糧を生産できるか)が向上すると、社会全体として、本人自身は直接的には食糧生産に携わらない人達を養うことが可能になる。これら直接には食糧生産に携わらない人達の住む場所が都市であり、彼らが都市の文化の担い手となる。この扶養家族とでもいえるような都市住民を養うことを可能にしたのが灌漑農業であった。耕地を人工的に潤す灌漑農業は、雨水頼みの天水農業に較べて農業の土地生産性を向上させ、それが結果として農業の労働生産性も向上させたものと考えられる。
農業はもともと計画を必要とする活動であったが、灌漑設備(排水設備)の建設などは、更に長期的な計画を必要とした。こうした状況の下で、計画する者(頭脳労働)と実行する者(肉体労働)の分離も生まれた。計画する者は命令する者でもあり、命令する者と命令される者(支配する者と支配される者)という上下関係をともなった社会の分離も生まれた。農耕を始め、都市文明を築いた人類は、土地を所有するようになったが、農民は土地の付属物のようになっていった。
3. 文明と森林破壊
メソポタミア、クレタ、ギリシャなどの古代文明は、その最盛期を迎えるとほどなく衰退し滅亡していったが、その背景には共通して森林破壊が見られた。灌漑農地と都市からなる文明は、耕地の拡大と、建築用や燃料用の木材需要を賄うために森林を伐採していった。人口増加と食糧増産のイタチごっこは人類が農耕をはじめて以来のものであるが、このことは古代文明にも当てはまる。地中海地域の森林破壊と都市文明の衰退は、概ね次のようなパターンを持っていた。
耕地の拡大も当初は平坦地への拡大であったが、人口の増加とともに遂には傾斜地へも耕作地を拡げざるを得なくなっていく。傾斜地の森林を伐採して切り開いた耕地でも短期間は収穫が得られた。しかし、森林を失った傾斜地の土壌は浸食を受けやすく、表土が失われるとともに収穫が得られなくなっていった。
また、上流部での森林伐採にともなう土壌浸食は、都市周辺の灌漑水路や排水路の閉塞をまねき、平坦地の耕地をも使用不能にしていった。こうして人口増加に食糧生産が追いつかなくなると、植民地が建設され、そこで食糧を生産して本国に送った。しかし、土壌浸食は食糧を荷揚げする港湾をも閉塞させ、土砂の堆積によってかつての港湾都市が内陸化すると都市は衰退し、ついには放棄された。
4. 文明と土壌劣化
多くの古代文明が再生可能資源である森林をその再生速度を上回る速さで利用し、森林ストックを使い尽くして衰退していったが、このことは土壌にも当てはまる。厚く堆積した土壌も自然の生態系が作った再生可能資源のストックであり、その厚みの増減は、土壌の生成速度と浸食速度の差によって決まる。人間は堆肥等の有機物を土壌に返すことにより土壌生成を助け、また、階段耕作などを行うことにより土壌浸食を緩和することができるが、ほとんどの場合、耕地では土壌の浸食速度が生成速度を上回ってきた。
結局のところ、単純化すれば、文明の寿命は、元々の土壌の厚みと正味の土壌浸食速度で決まると考えて差し支えない
( 文明の寿命=元々の土壌の厚み÷(土壌浸食速度−自然の土壌生成速度−人為的土壌生成速度))。
一つの場所で文明が繁栄できるのは30〜70世代(1世代30年として900〜2000年)程度であり、文明は土壌のストックを使い尽くしては衰退していった。アジアの米作地帯を除けば、例外となるのは、毎年定期的に氾濫し、豊かな養分を耕地に供給するナイル川に支えられたエジプト文明くらいのものである。
5. 持続可能文明としての江戸
江戸時代の持続性の鍵は、近畿などの一部の地域を除き、森林を維持できたことにある。それを可能にしたのは、「消費側の抑制による木材消費量の安定化」と「天然林を伐採する採集型林業から植林と育林を行う育成型林業への転換」であった。これによって日本の江戸時代は比較的高度な文明を維持し得たわけであるが、その期間は300年弱に過ぎず、森林や土壌を使い尽くして衰退していった古代文明の存続期間よりも短い。
日本の森林率は現在でも60%以上あり先進国の中では例外的に高いのは事実であるが、江戸時代の日本のやり方がエジプト文明並みの持続性を持つかどうかは検討の余地がある。江戸時代の1人当たりの耕地面積は、人口増加に伴って1600年頃の1.79反から1830年頃には0.94反へと減少しており、江戸時代の土地への人口圧力は限界的な状況にあったことが推察される。
このページのトップへ