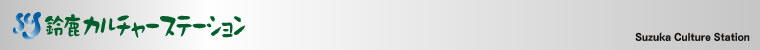
教師の一言が生徒との壁に
第20回大嶋講座と映画レビュー 『パリ20区、僕たちのクラス』(2008年、監督ローラン・カンテ)
記者のレポート編 >>>吉田さんのレポートに戻る
 日本の映画ポスター
日本の映画ポスター
イメージとは違う内容
映画『パリ20区、僕たちのクラス』、日本語のタイトルやポスターからは、何か明るいイメージが伝わってくる。教師と生徒の友情を綴った学園ドラマのような。ところが、とんでもない、これはフランスの現実を赤裸々に描いたドキュメンタリーと言えるだろう。
その原題を大嶋さんがまず明らかにする。
「原題は『entre les murs』、直訳は、“壁の間で”、教師と生徒の間にある壁、という意味です。お互いの間に壁がある。生徒が心を閉ざしてしまう、噛み合わない。それを象徴した言葉です」
教師の苦悩・葛藤が綴られているという。実際に教鞭をとっていた先生自身が原作者で、映画の主演もつとめ、生徒たちもみな素人の現実に近い設定だという。作者の体験に基づく実録であり、パリの問題校と言われる学校風景を扱った記録映画とも言える作品だ。
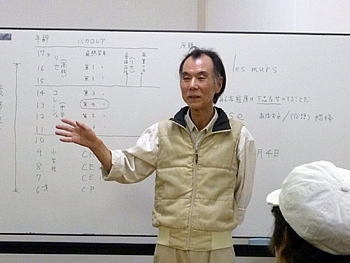
講師の大嶋優さん(関西学院大学フランス語講師・翻訳家)
家庭教師時代の3つの体験談
大嶋さんが何故この映画を取り上げたか、ここで自身のエピソードが明かされる。
大嶋さんは、個人的な体験を講座で述べることに、かなり躊躇していた。というのも、言葉に対する警戒心があり、「言葉には、一言で生徒の人生まで変えてしまう恐れがある」と危惧しているからだ。それは大嶋さんの体験からくるもので、映画の内容とも直結する問題を孕んでいた。故に客観性のない体験談を明かすことは、それだけ勇気の入ることだったと推察する。それでも、その心情を明かすことで、言葉の重みを実感あるものとして伝えてくれた。
まず、「個人的なことになりますが」と前置きした後で家庭教師時代の体験を話した。
「私も大学の頃、小学5年生のお子さんの家庭教師をしていました。その子は、10分と椅子に座っていられない。勉強というよりもいかに机の前に座らせることが出来るか、そのことに半年ほど四苦八苦しました。座り出すと成績も上がってきた。子ども達は絶えず、落ち着きがなく、それは子どもの習性かもしれませんが、10分でも座って聴くことがなかなか難しい。それを実感したのが一つです」
二つ目は一言の大きさを知ったというエピソードだった。
「次に、中学生の女の子ですが、非常におませな子でした。勉強はよく出来るんですが、一言一言の言葉に対する反応が非常に鋭く、逆を突かれて、対応に苦慮しました。勉強よりも、一人ひとりを知るというのは難しいと思いました。
ある時、その子の胸元が少し広い服を着ていたので、『胸見えるよ』って言ってしまったら、次の日親御さんから『来なくてよろしい』と言われまして、たった一言の言葉が、子どもには、やはりすごい衝撃だったのか、日本の場合はすぐに親に伝わり、跳ね返ってきたことがありました」
そして三つ目――
「次に大学院の頃ですが、悪い言葉ですが、洟垂れ小僧がいまして、勉強は出来るんですが、鼻水をかまずに、すするんです。ずるずると。私はそれが嫌いで、ティッシュを渡して、『鼻かみなさい』と言っても聞かない。で、私自身その子に対して、憎たらしいという思いが出てしまって、ゲンコツを―-― 普通は軽くポンと叩いたりするんですが、今思うと、意識的に強く叩いた感じがするんですね。それで彼の表情が変わり、やがて涙を流したりした。その時の僕の感情が、未だに記憶に残っていて、トラウマといいますか、それ以来、人を殴ったり叩いたりということは決してありません。未だに彼のその時の表情は僕の頭にこびり付いているんです」
大嶋さんは、その生徒にとった行動を今でも悔いているようだった。一言一言が重かった。そして映画の内容へと向けられた。
 国語教師のフランソワ先生
国語教師のフランソワ先生
言葉の解釈の違いから
「フランソワ先生は決して暴力を振るわない。生徒と対立的になっても暴力で解決しようとはしなかった」と主人公であるフランソワ先生を讃えた。
なぜ、大嶋さんはこんな話をしたのか、映画を見ればすぐに分かった。
フランソワ先生も、生徒に発した一言から、事件が起こり、男子学生が退学処分となる事態に至る。
「一言の重さ」、迂闊に使った言葉でも受け止め方によって深く傷つくことがある。教師と生徒の隔たり、壁となって、逆に言葉が立ちはだかってしまう。それを物語っていた。
事態の原因は、教師の使った言葉の意味と、生徒が受け取った言葉の意味に大きな隔たりがあったことだ。
先生の一言に教室は騒然となる
国語教師のフランソワ先生は、女子生徒の態度がはしたないことを、「ペタス」だと指摘した。それは、「下品な女のすることだ」という比喩として使った言葉だった。ところが、生徒の方は、「ペタス」を、俗語の「娼婦」という意味に受け取る。生徒からすると「娼婦呼ばわれされた」、侮辱されたとなり、教室は騒然となる。そこに男子生徒スレイマンが先生に噛みついていく。鞄を振り回し、近くの女子生徒の顔に当たり怪我をさせてしまう。そのことから、普段からも問題児とされていたスレイマンは退学処分となる。彼はアフリカのマリ出身で、退学となると両親ともに強制送還となる。マリは未だ内戦状態だという。
日本では考えにくい状況だが、子どもたちはそんな中で絶えず怯えながら、暮らしているような印象をもった。
 中国人のウェイ
中国人のウェイ
そうした子どもを取り巻く環境が、様々な場面で浮き彫りにされる。
中国出身の男子生徒ウェイの母親もある日突然、不法滞在で検挙されてしまう。移住して3年にもなるというのに。ウェイは成績もよい優良生徒で先生からの信頼も厚い。教師たちは、なんとか食い止めようと裁判費用のカンパを募る場面もある。
 卒業後を憂う
卒業後を憂う
年度末の終了日に、ある女子生徒が、フランソワ先生に、「私は、この一年で学んだことが何もない」と悲しそうに言い寄る。そして「就職コースはイヤ」と訴える。
フランスの教育制度では、5・4・3制で、中学校は4年間だ。飛び級や落第もある。中学後の進路は普通高校か職業高校に分かれる。先生は「まだ就職コースと決まったわけじゃない。来年の成績しだいだ」とあと一年頑張るように励ます。
その女子生徒の切実に訴える姿には、胸に突き刺すような痛みを感じた。子どもがこんなにも自分の将来に不安を抱いているのか、と。その子が見せる表情は、痛々しかった。
教師がどう子どもを見ているか
問題を起こす生徒を懲罰によって取り締まろうという考え方はフランソワも反対意見を持つ。「生徒の好奇心を引き出すべきだ」と。ところが、スクリーンに映るフランソワ先生の態度は、時に抗戦的で、教師の立場を行使して命令を下す。それには生徒側も、反発する。誰も命令に屈したくない。指示がいくら正しいとしても、服従を嫌う。従うことは、屈辱感が伴うからだ。
 先生の評価に照れるスレイマン
先生の評価に照れるスレイマン
一方、生徒の中にある芽を引き出そうとした時は、生徒も積極的になる。自分の意見を発表し、新しいことへの興味を示しチャレンジする。問題児のスレイマンでも終始反発しているわけではない。課題の自己紹介文を書くのに、文章が苦手なため、写真を撮って表現した。先生は、その良さに着目して、写真にキャプションを付けることを指示する。スレイマンは、素直に取り組んだ。出来にも満足し、先生にも褒められた。
この映像が、嘘か真か、たんなる演出かわからないが、教師と生徒がフラットな関係にある時は、互いに穏やかで、意思疎通が見られる。ところが、一旦バランスが崩れると、たちまち、シーソーのような力関係が働き、摩擦や亀裂となり、「教師と生徒の壁」が生じる。常時ある訳ではないのだ。
むしろ教師が生徒をどう見ているか、そこに「壁」を取り去る手がかりはあるように思う。
職員の議論の端に生徒への見方を覗かせる。次の言葉は教師の発言だ。
「手強い生徒たちですが、根は可愛い連中です」
「クズで無知なガキどものくせに、教えようとするとこっちを無視する」
 生徒をボヤく先生
生徒をボヤく先生
教師が苦労する2つの問題
現場の当事者でも、教育専門家でもない記者が、スクリーンの姿を分析・批評してもナンセンスだろうが、それを承知上でレポートを続けよう。
教師は、生徒に新しい知識を習得させることと同時に、授業態度や生活態度のルールを守れるように指導が求められる。大嶋さんが小学5年生の子の学習態度に四苦八苦したという例と同じだ。そこには子どもに対する躾という問題が含まれている。
つまり、教師は、無理なことを二つ同時に子どもたちに強要していることになる。
子ども側からすれば、興味のないことでも、覚えなくてはいけない、という無理。
さらに 、机に座っていなくてはならない、という無理。
この二つの無理が働いていることになる。
状況が違うと、一転する。パソコンゲームの前では何時間でも夢中になっているし、
身動き一つしないで、画面に向き合っている子どもを見かける。
生徒は、教師の“無理”の押し付けに反発しているのではないか。
現代社会は、すでに社会の大きなシステムの中にある。教育制度や法律や常識や世間体や… それらに教師も縛られ、親も縛られて、身動きが出来ず、その枠組みの中に、また子どもを押し込もうとしているように思えてならない。
 自己主張は旺盛
自己主張は旺盛
自由闊達な学びの場を!
本当にこれでいいのだろうか?
子どもは、まったく純真無垢に生まれてきているのに。
人類は、連綿と子孫を残し連続する中にあっても、一人一人は、まっさらな生命体として地上に誕生している。にも関わらず、古い因習に染まってしまうのだ。
子どもを野放図に、無知のままに育てろ! ということが言いたい訳ではない。
自由奔放にしたら、何をするか分からない。子どもは残酷なことを平気でする。という意見もあろう。
一方で、子どもは本来、知りたがり、やりたがり、だとも言える。
好奇心旺盛で、興味あることには「何で?何で?」と探求心もある。
未知のエネルギーに溢れている。
子どもの本来の姿をどう観るか、どちらを伸ばすか、大人の目に懸かっているのではないだろうか。
大人たちの悪しき習慣の社会でしたたかに生きる術を、子どもたちに強いるのでなく、 伸び伸びと自由闊達に過ごせる環境をつくり、その広場の中に子どもたちを放てば自然と成長していけるような学びの場を作りたいと思うが、どうだろうか。
その理想を実現しようとしているのが、このカルチャーステーションの志とも言える。
まずは、始めないことには、何も変わらない。
ちょっと飛躍してしまったが、日頃思っていることがつい出てしまった。
最後に参加者のTさんが寄せてくれた感想を紹介して終わりたい。(記者:いわた)
先生のたった一言で30年間傷ついたままだった
言葉の意味の取り違えで起こる問題は無数にある。
相手の真意を聴こうとする前に、自分がどう受け止めたかが問題となる。その結果、怒りや悲しみの感情が湧いてくる。冷静に考えてみると、とても滑稽なことだと思う。自分が勝手に解釈したことで、自分が怒っているのだから。しかし普通は、「そう言った」「そういう言葉を使ったから」と、相手のせいにする。一度引き出された感情は後戻りできない。言った相手に感情をぶつけるか。あるいは、その言葉で自分を傷つける。
「たった一言」だが、傷は傷として残っていく。
私は、中学3年の時、その一言で大きく傷ついた経験がある。
やはり国語の先生から言われた一言だった。その言葉はここでは明記しないが、その言葉によって私は、自分がまったく価値のない人間だと思い込んでしまった。
そして反発心も湧いた。必ず見返してやる。そして普通とは違う人間になってやると。それから私は、物事を必ず斜めに観る癖がついた。ごく普通の平凡な人間にはなりたくない、と思った。
私は、ありのままの自分を素直に認めることが出来ずに、その呪縛から約30年、常にその傷ついた心のまま、その言葉から逃れようと意識してきた。
自分の一挙手一投足が、その言葉から逃れるための行為行動だった。
大嶋さんの発言通り、「たった一言の言葉はその人の人生を変える」と言える体験を自らが経験していただけに、大嶋さんの話は心に響いた。
その正体が見えてくれば…
中学を卒業して30年も経てば、傷つけた言葉の効力も次第に失われ、ありのままの自分であることを認められるようにはなってきた。逆に、なぜ、その言葉にあれだけ反発したのだろうか、その時、教師の言葉を自分がどう受け取ったのだろうか――「お前なんて、平々凡々でなんの魅力もない男だ」という意味に自分は勝手に思い込んだのだった。実際には、そういう言葉を使ったわけではなかったのに。これも自作自演の思い込みなのだが。言葉は、自分の中にある何かを引き出す働きがある。受け手の深層にあるものに反応する。そこに何かがあるだろうか。また、相手側の深層からのつぶやきだったとしても、言葉じりではない真意があるはずだ。
人と人との基本的な会話すら、誤解曲解の問題を孕みながら、日々過ごしている。そしてイラついたり、キレたりして仲悪くなる。喧嘩・暴力へも発展する。
こうした問題の基には、自分勝手な解釈というものがある。感情をむき出してしまっては、その原因について冷静には考えられないが、日々、そういう人としての基本的な生態を自覚し、注意を向けていたら、ずいぶんと違う人生になったことだろう。
私は、カルチャーステーションにある「サイエンズスクール」のセミナーや合宿に参加し、人と人との基本的な対話のあり方や人や社会の本質について探求している。30年に渡る心の傷もそんな場で癒されてきた。
子どもから大人に成長する段階で、人とはどういうものか、そういうことを知り・自覚しながら、その上に知識や経験を積んでいくことが本当は大切で、幸せに生きる術だと思っている。(T)
>>>参加者 吉田さんのレポートに戻る
次回のお知らせ

